前回に続いて私の所属流派である芦原空手(芦原会館)のおすすめ本について、記載します。
最初に結論です。
おすすめは、以下8冊です。
①実戦!芦原カラテ1
②実戦!芦原カラテ2
③実戦!芦原カラテ3
④芦原英幸 サバキの神髄
⑤最強格闘技図鑑
⑥最強格闘技図鑑 真伝
⑦空手に燃え、空手に生きる
⑧流浪空手(さすらいからて)
どれも私が実際に保持している本です。
今回は、④~⑥について、記載します。
全て、松宮康生先生の書籍です。
松宮先生は芦原英幸先生に直接師事を受けられた武道家です。
特に、芦原英幸先生の鍛錬メニューが書かれている箇所を抜粋します。
よって、芦原空手を含むサバキ系空手に特化した内容です。
関係者に少しでも参考になれば幸いです。
次から、深堀りしていきます。
↓前回記事
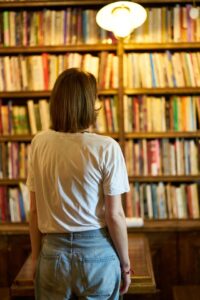
④芦原英幸 サバキの神髄
最初に紹介する本書籍は、芦原空手経験者向けです。
芦原空手歴15年以上の私からすると目からウロコ的な内容が多々あります。
中でも、特に気に入っている箇所を1点だけ記載します。
『弟5章:芦原カラテ’サバキ’の進化』
の72ページ目より、私が最も影響を受けた、1文を抜粋します。
芦原は、晩年にも朝起きてから「四股踏み」や「股割り」のトレーニングを自宅のベランダで行っていた。
私はこの章を読んで、超人的な空手家の動きに近づくには、股関節の柔軟性が必須で、そのための鍛錬は長期継続すべきと考えるようになりました。
今でも、自分の自主トレメニューに、「四股踏み」を組み込んでいます。
また、主催する支部道場の稽古で、騎馬立ちからの「前回り鉄槌」・「後ろ蹴り鉄槌」を入れているのは、本書籍の影響です。
繰り返しになりますが、本書には、他にもサバキ技術向上のために有益な内容が多々あります。
⑤最強格闘技図鑑
本書は、芦原空手だけでなく、格闘技全般を対象にした書籍です。
中でも、芦原空手に特化していて、私がとても参考になった内容を記載します。
『弟1章 芦原空手 芦原英幸 空手技術の革命・サバキ』
の64~65ページに、芦原英幸先生が基礎体力をつけるために特に重要視したトレーニングの記載があります。
①首を鍛える逆立ち
②柔軟性をつけるストレッチ
③パワー・トレーニング(ウエイトトレーニング)
④スタミナをつけるためのトレーニング(ランニング等)
⑤腹筋と腕立て伏せ(毎回の稽古で)
本書籍を参考に、現在の私の補強鍛錬メニューを考えています。
また、私の運営する支部道場では、稽古の最後に取り入れている補強メニューの参考としています。
1点だけ相違があるのは、私は自重トレーニング派のため、パワートレーニングのためには、ウエイトを使用を使用していません。
まあ、自分の体重をウエイトとして見ると同じかもしれませんね。

⑥最強格闘技図鑑 真伝
上述の「最強格闘技図鑑」の続編で、芦原空手だけでなく、格闘技全般を対象にした書籍です。
中でも私が最も参考になった箇所を1点だけ挙げると、
で、具体的には、『弟2章 芦原英幸』 の 21~23ページ目の「芦原英幸の太氣拳」 です。
実は、私が太氣拳に興味を持ち出したキッカケが本書です。
後年には、太氣拳専門の技術書も買いました。
↓参考書籍↓ 購入した太氣拳技術書
本書に記載されている芦原先生の太氣拳メニューは、「立禅」「這い」です。
実際に「立禅」「這い」の鍛錬を継続してみると・・・
本当に、本書に記載されている効果を得ることができました。
具体的な効果は以下記事にしたので、参考にどうぞ。



注意書きとして、私の「立禅」「這い」は、独学のため、どこかに習いに行ったことはないです。
あくまで書籍・動画をヒントに鍛錬しています。
中国拳法専門の方から見たら見解違うかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。
まとめ
今回は、芦原空手(芦原会館)のおすすめの本を3冊記載しました。
④芦原英幸 サバキの神髄
⑤最強格闘技図鑑
⑥最強格闘技図鑑 真伝
最後になりますが、
私が「⑤最強格闘技図鑑」、「⑥最強格闘技図鑑 真伝」を購入したキッカケは、黒帯になり数年経過し、
どうしたら芦原英幸先生のような達人の動きに近づくことができるのか?
達人用の特別な鍛錬メニューがあるものか?
を研究したいと思い、達人の鍛錬の軌跡を追いたいと考えるようになりました。
そのヒントがこれら2冊には入っていました。
上記2冊より、後年に購入した「④芦原英幸 サバキの神髄」でも、達人の自主トレメニューの掲載がありました。
私は今回の3冊に記載ある達人の稽古方法を、現在の自主トレ、または、運営する道場の稽古メニューに取り入れています。
空手人生に多大な影響を与えた3冊です!
繰り返しになりますが、今回は、芦原英幸先生の鍛錬メニューが書かれている箇所のみを抜粋しましたが、もちろん他にも武力UPのために、有益な内容が多々あります。
3冊ともに稀にみる良書なので、興味がある方は、是非手に取って読んでいただければ幸いです。
今回は以上です。
以下記事も参考にどうぞ!



